- TOP »
- 法人設立お役立ち情報 »
- その他 »
- その他税務
ロイヤルティ(無形資産の使用料)の授受を巡る国際税務上のさじ加減
日本の親会社が海外の製造子会社等に自社で醸成した技術やノウハウ等の無形資産を使用させる場合、その親子企業間では通常、何らかの金銭の授受が発生します。その金銭の授受は別名、「ロイヤルティ」と呼ばれ、無形資産から発生する"価値"を海外子会社が親会社から拝借する=使用料を支払うことで成立します。
このロイヤルティに係る独立企業間価格(料率)の決め方については、以下にあげる2つが中心として考えられています。
(1)ロイヤルティの水準を直接見る方法
(2)ロイヤルティ控除後の海外子会社の営業利益を見る方法
まず、上記(1)のロイヤルティの水準を直接見る方法としては、独立価格比準法(CUP法)的な方法の適用が考えられ、実務的には各種ロイヤルティのデータベース等から同種の無形資産取引を比較対象としていくつかピックアップを行い、それらをもって裏付けとするやり方です。
他方、(2)のロイヤルティ控除後の海外子会社の営業利益を見る方法としては、実務上は取引単位営業利益法(略称:TNMM)を使用し海外子会社の営業利益水準の裏付けとする方法が多く用いられています。即ちこれは、海外子会社自体が重要な無形資産を有しておらず単純な製造機能のみを持つだけにとどまる為、ロイヤルティ控除後の営業利益が同様の状況にある他の現地製造子会社と同じようなレベルになるようにその水準を(逆算するような形で)設定して行くと言う考え方です。
勿論、海外子会社は日本親会社の技術やノウハウを使用しているのでそこから生じる超過利益を一旦は直接享受する形になります。しかしながら、一方では日本の親会社に対してその後にそれ相応のロイヤルティ支払を行うこととなる為、ロイヤルティ支払後の営業利益率と言うのは基本的な製造機能のみに対応する水準(つまり、現地の同業他社と同水準)となるはずであり、TNMMはこの点に着目していると言えるのです。
この点で注意しなくてはならないことと言うのは、仮に海外製造子会社の営業利益率が比較対象に比べて低過ぎたりした場合、海外の税務局に本社へのロイヤルティ支払の高さを問題視されるなどの誤解&トラブルも内包する(特に中国)ので、結果的に場合によっては損金性が否認される(損金算入不可)可能性も含んでいますので安心は出来ません。
以上、総じて経営の観点から本件を鑑みますと海外子会社が高収益を上げることは一様に望ましいことと言えますが、税務局の視点から眺めて行くとこの状況は必ずしも喜ばしい状況ではないと言うのはお分かりになられたのではないでしょうか?
何故なら海外子会社の利益率などが高過ぎると税務局的には「利益移転」を意図的に行なっているのではないか?と疑いをかけられたり、その逆となると今度は当地の税務局から損金算入不可の可能性をチラつかされる...。
企業の課税対象額の水準を(どのレベルに設定して行くのか?)と言う議題は、この様にかくも難しいテーマであると言うことが、このロイヤルティの扱いからも垣間見えるのではないでしょうか。

















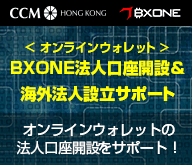

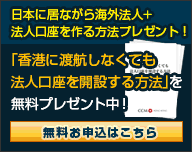





 その他
その他