- TOP »
- 法人設立お役立ち情報 »
- その他 »
- その他税務
今一度考える、居住・非居住者判定基準の"定義"
日本は「高税率国」として世界でも突出した国のひとつとして認識されています。所得税の最高税率と言うのは45%であり更に住民税(10%)がこれに上乗せされると言う構造を考えると、誠に不名誉なことではありますが、社会システムの構造上、富裕層が生まれ難い環境と形容しても決して言い過ぎではないことでしょう。
こうしたこともあり、富裕層や高額所得者が海外移住を実行したり海外へ資産を移そうと言うアクションを検討せざるを得ないと言うのは、これは半ば致し方が無い「自然の摂理」のひとつと言えることなのかも知れません。
さて、そんな背景の中で今回ご案内する内容と言うのはこうした海外をベースにされる方々にとって最大の関心事のひとつである「居住・非居住」となる訳ですが、今回はその判定基準に関した解釈についてご案内致します。
◼️非居住者の判定
(1) 概要
・居住者、非居住者の「定義」
所得税法では、居住者は、国内に住所を有する者又は現在まで一年以上国内に居住する者とされています。非居住者は、居住者以外の者とされています。
また、この定義に加えて推定規定と言うものがあり、それは(居住者に関しては)継続して1年以上国内に居住することが必要となる職業を有する者、(非居住者に関しては)継続して1年以上国外に居住することが必要となる職業を有する者とされています。この推定規定は、多くの場合、海外から日本法人に赴任した外国人あるいは海外赴任した日本の会社員が該当すると言うものです。
留意事項としては、以下のことが挙げられます。
1)1年以上海外勤務が命じられたサラリーマンは、その出国時から非居住者となる。
2)1年以上海外居住が必要な職業を有しない場合には、国内と国外とのいずれに住所があるか否かにより判断することになる。
3)租税条約の規定により、判定期間が短くなる場合がある。
最初の留意事項1ですが、居住者か非居住者かの判断に関しては、日本の場合、課税期間に関係なく判断する形をとっています。
具体的には1年以上の海外勤務を命じられて出国する場合には、その出国の日からその者は"非居住者"となり、帰国した場合にはその入国日の翌日から"居住者"に復帰します。また、住所が日本から海外移住に移転するような場合、その移転の日に日本にとってその者は"非居住者"となり、海外から日本に住所が移転した場合には、その日から日本の"居住者"となります。
例えば、海外に転居したが(子供を日本の学校に通わせたいとして)日本に帰国した場合、その帰国した日の翌日から日本の居住者になると言うものです。
次に、2の部分、所謂住所がどこにあるのかについての解釈があります。先ず「住所」の定義ですが、日本の民法では、"生活の本拠"とされています。これだけでは何のことやらわかりませんが、東京高裁の平成20年1月23日の判決(武富士事件の高裁判決)では次のような判断要素を上げています。
それは、住居及び居住実態、職業、生計を一にする配偶者や親族の居住場所、財産の所在地等、客観的に観察できる居住意思の要素のことであり、これらを総合的に検討して真の住所地を判断して行くと言うものです。
上記の中で、特に一番判定し難い部分と言うものは、客観的に観察できる居住意思と言うやつですが、これは海外移住をするとの意思は、その本人の内面の意思であり表面上での確認項目は曖昧と判断されがちではありますが、これは海外移住をするために様々な手続きや通知、挨拶といった本人の行動から客観的に観察できる部分から本人の居住意思を確認すると言うものです。
最後に3の租税条約の規定によって判定機関が短くなると言う部分については、赴任先国と日本の間で締結された内容によって変わる為、ここは香港との間でのものに限らせて頂きますが、香港では60日を超える滞在日数を行う者について現地での納税義務発生を謳っています。
その意味で言うと、赴任期間が最初から3年等と言われた状態で香港赴任となる方については、香港支給の現地所得については日本での納税義務から除外される形になりますのでこの面では軽税率を初めから享受出来る有利な立場となることをご留意頂いても良いでしょう。
このように、住所地の判断は、事実認定の問題であり、個々の事例により個別に判断すべきケースが多いと言う事を、改めて押さえて置く必要はあります。

















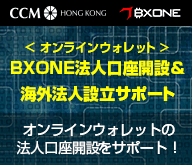

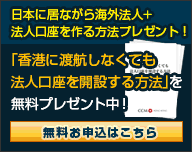





 その他
その他