- TOP »
- 法人設立お役立ち情報 »
- その他 »
- その他法人
独立企業間価格?無形資産?ロイヤリティ?多方面で検討しておかなくてはならない海外製造拠点との関係
海外に製造子会社を設立するような場合、日本の親会社が製造技術などを供与する、より正確には、日本の親会社が保有する特許権やその他のノウハウを子会社に使用させるケースが多数存在します。例えばですが、香港に100%子会社等を設置し、その会社から中国などに製造拠点を構えるスタイルが一般的となって久しいですが、その際にも親・子・孫の関係の中でこうした特許を巡る取扱いが存在することは明らかです。
そして、こうした場合に先ず注意しなくてはならないことと言うのは、税務上の取り扱いとなります。所謂、移転価格税制がそのキーポイントとなりますが、この移転価格税制は棚卸資産などの有形資産取引種に適用されるものだけではなく、上述の特許権やノウハウと言った無形資産(*)の使用料もその対象となることを忘れてはいけません。
(*)無形資産とは重要は価値を有し所得の源泉となるものです。具体的には①技術革新を要因として形成される特許権や営業上の秘密事項等、②従業員等が経営、営業、生産、研究開発、販売促進などの企業活動における経験等を通じて形成したノウハウ等、③生産の工程、交渉手順や開発、販売促進、資金調達等に係る取引網等
日本の親会社が海外の製造子会社にその技術やノウハウ等の無形資産を使用させるような場合(特にその子会社が直接外部に製品販売をしているケース)、日本の親会社は通常ロイヤリティをそこから回収していると考えられます。
仮にこれを香港の統括会社を経由する(間に入る)としても実質的にこの権利を有しているのは日本の親会社になりますので、この場合は香港の子会社と日本の親会社との間にもロイヤリティに対するトランザクションが発生すると考えても良いでしょう。つまり、このロイヤリティの位置付けと言うのは海外側(海外子会社や海外孫会社)の超過利益の回収を意味することになるのです。
ではこのロイヤリティに係る独立企業間価格(料率)の決め方というのは如何でしょうか?
その方法としては2つあり、先ず、①ロイヤリティの水準を直接見る方法、と②ロイヤリティ控除後の海外子会社の営業利益を見る方法、です。①に関する具体的な手段と言うのは独立価格比準法(CUP法)的な方法の適用が考えられ、これは実務的には各種ロイヤリティのデータベースを照会→比較対象(同種の無形資産取引)を選択して価格のロジックの裏付けを行うというものです。
これに対し②の方法というのは実務上は取引単位営業利益法(TNMM)を使用し海外子会社の営業利益水準の裏付けをすると言うものです。
即ち、海外子会社・孫会社と言うのは多くのケースで自らが重要な無形資産を有していると言う訳ではなく、単純な"製造機能"のみを所有すると言う傾向が強い為、ロイヤリティ控除後の営業利益が同様の状況にある他の現地製造会社と同水準になるように設定されるべきであると言う考え方が根底に流れていると言うことなのです。
勿論、実務的には海外子会社や孫会社は所在国などでの内国取引でも(日本の親会社の)技術やノウハウを利用した製品の販売から利益を得ている為、そこから生じる超過分(利益)については一旦享受することになります。
しかしながら、ここから得る利益から日本の親会社に対して見合いのロイヤリティ支払いを同時に負うことにもなる為、親会社に対してロイヤリティ支払いが完了した後の営業利益率というのは製造機能のみに対応する水準のものとなる筈であり、故にTNMMはこの点に着目しているのです。
然しながら、仮にこれらの手続を正確に処理したとしても、どちらか(日本vs海外)一方にどうしても利益が偏るケースも散見されることがあり、この場合は日本の税務対応だけに留まらず、進出先での税務対応も視野に入れておく必要があります。
特に日本と海外製造子会社の間に香港やシンガポールと言ったタックスヘイブン地域・国に在する統括法人が存在する場合は、税務署的には一段厳しい査定になる可能性を含んでいることを忘れてはなりません。
独立企業間価格?無形資産?ロイヤリティ?多方面で検討しておかなくてはならない海外製造拠点との関係
海外に製造子会社を設立するような場合、日本の親会社が製造技術などを供与する、より正確には、日本の親会社が保有する特許権やその他のノウハウを子会社に使用させるケースが多数存在します。例えばですが、香港に100%子会社等を設置し、その会社から中国などに製造拠点を構えるスタイルが一般的となって久しいですが、その際にも親・子・孫の関係の中でこうした特許を巡る取扱いが存在することは明らかです。
そして、こうした場合に先ず注意しなくてはならないことと言うのは、税務上の取り扱いとなります。所謂、移転価格税制がそのキーポイントとなりますが、この移転価格税制は棚卸資産などの有形資産取引種に適用されるものだけではなく、上述の特許権やノウハウと言った無形資産(*)の使用料もその対象となることを忘れてはいけません。
(*)無形資産とは重要は価値を有し所得の源泉となるものです。具体的には①技術革新を要因として形成される特許権や営業上の秘密事項等、②従業員等が経営、営業、生産、研究開発、販売促進などの企業活動における経験等を通じて形成したノウハウ等、③生産の工程、交渉手順や開発、販売促進、資金調達等に係る取引網等
日本の親会社が海外の製造子会社にその技術やノウハウ等の無形資産を使用させるような場合(特にその子会社が直接外部に製品販売をしているケース)、日本の親会社は通常ロイヤリティをそこから回収していると考えられます。
仮にこれを香港の統括会社を経由する(間に入る)としても実質的にこの権利を有しているのは日本の親会社になりますので、この場合は香港の子会社と日本の親会社との間にもロイヤリティに対するトランザクションが発生すると考えても良いでしょう。つまり、このロイヤリティの位置付けと言うのは海外側(海外子会社や海外孫会社)の超過利益の回収を意味することになるのです。
ではこのロイヤリティに係る独立企業間価格(料率)の決め方というのは如何でしょうか?
その方法としては2つあり、先ず、①ロイヤリティの水準を直接見る方法、と②ロイヤリティ控除後の海外子会社の営業利益を見る方法、です。①に関する具体的な手段と言うのは独立価格比準法(CUP法)的な方法の適用が考えられ、これは実務的には各種ロイヤリティのデータベースを照会→比較対象(同種の無形資産取引)を選択して価格のロジックの裏付けを行うというものです。
これに対し②の方法というのは実務上は取引単位営業利益法(TNMM)を使用し海外子会社の営業利益水準の裏付けをすると言うものです。
即ち、海外子会社・孫会社と言うのは多くのケースで自らが重要な無形資産を有していると言う訳ではなく、単純な"製造機能"のみを所有すると言う傾向が強い為、ロイヤリティ控除後の営業利益が同様の状況にある他の現地製造会社と同水準になるように設定されるべきであると言う考え方が根底に流れていると言うことなのです。
勿論、実務的には海外子会社や孫会社は所在国などでの内国取引でも(日本の親会社の)技術やノウハウを利用した製品の販売から利益を得ている為、そこから生じる超過分(利益)については一旦享受することになります。
しかしながら、ここから得る利益から日本の親会社に対して見合いのロイヤリティ支払いを同時に負うことにもなる為、親会社に対してロイヤリティ支払いが完了した後の営業利益率というのは製造機能のみに対応する水準のものとなる筈であり、故にTNMMはこの点に着目しているのです。
然しながら、仮にこれらの手続を正確に処理したとしても、どちらか(日本vs海外)一方にどうしても利益が偏るケースも散見されることがあり、この場合は日本の税務対応だけに留まらず、進出先での税務対応も視野に入れておく必要があります。
特に日本と海外製造子会社の間に香港やシンガポールと言ったタックスヘイブン地域・国に在する統括法人が存在する場合は、税務署的には一段厳しい査定になる可能性を含んでいることを忘れてはなりません。

















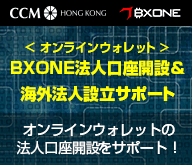

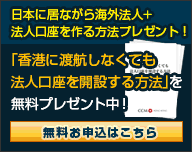





 香港
香港 その他
その他