香港 > 一般
在香港の人々及び企業の選択オプションとはどんなものなのか?
更新日:2020年10月29日
中国の国家安全維持法が可決し施行した今年の6月30日以降、在香港の人達、特にマジョリティーを占める香港人や、香港経済の重要なピースである外国企業にとって(このまま香港に留まるべきか否か?)と自問自答する日々が続いています。
この新法の骨子は中国政府が定義している転覆、離反、テロリズム、外国勢力との共謀など理由として、今後の市民生活を取り締まって行く内容のものです。現実的な視点では、この法について関わる層というのが極一部とされていますが、その反面、この条項自体が非常に曖昧な表現にとどまっていると言うこともあり、拡大解釈によっては、実際のテロリズムのような大事件から習近平国家主席を扱った風刺画に至るまで、言わば無制限の範囲で適用される可能性を含んでいるものと言えます。
つまり、仮に中国や香港外の国・地域で共産党を批判した内容のSNSを発信した一個人が居たとして、数年後に観光等の目的でその者が香港入りした際、この法律に基づいて突然逮捕され、中国本土に送還→裁判に掛けられると言う可能性が出て来ると言うものなのです。
ちなみに香港は現在、民主主義国との間で20の引き渡し条約を結んでいますが、香港の法制度(基本法)が中国の国家安全維持法によるこのような攻撃を受けた後では、この条約を維持して行くことは難しいと判断し、米国、カナダ、オーストラリアの3国は既にこの条約を停止する決定をしました。
この様に、中国共産党が"好ましくない"と判断する行為を行った人間や会社の動き等は、一様に中国国内での全体主義的で不正且つ不公平な起訴の対象となり得る可能性を含んでおり、これをいち早く察知したメディア等は既に具体的なアクションを実施し始めています。
例えば米国系メディアの代表格であるニューヨークタイムズ紙は国家安全維持法が施行してから何と2週間後の7月半ば、同社デジタルニュース部門の香港撤退を発表したり(行き先は韓国ソウル)、その他(ワシントンポストやウォールストリートジャーナル等)もNYタイムズに追従することを検討してしていると噂されています。
では、個人レベルではどのようにこの国家安全維持法が捉えられ、そしてその対抗策が検討されているのでしょうか?香港居住者のマジョリティーを占める香港人はもとより、その中でも特に「富裕層」と位置付けられる方々はこの"圧政開始"とも言える状況に対して一層の危機感を募らせています。
この1年の動きからも分かるように、香港の運命はもはや北京の判断次第になってしまっているのは事実であり、ゆえに自分達の富に対して大きな損失(或いは没収?)を被ると言った最悪のシナリオを想定しています。それゆえ、97年の返還前に起こった動きを踏襲し、現在は様々なルートを介して再移住の計画立案を行っている者も居ると伝えられています。
この様に"香港を離れる"と言う決断を香港富裕層が行った場合、その移住先の候補地としては先ず3つの国が上がります。
引合い場所の筆頭として頻繁に上がる国は香港と極似した金融システムを所有するシンガポールです。しかしながら、シンガポール政府自体の姿勢は慎重であり、移民歓迎の意向を示すことは(現時点では)行っていません。
その理由としてはシンガポールと中国の政府の関係が良好であると言う側面が存在するからです。亡命となる移民をここで受け入れてしまうことは国家間の対立を助長するものでしかなく、その観点を鑑みると亡命する香港人の為の受け皿となるのは現実的ではないと言えます。
では台湾はどうでしょうか?台湾は"国として"香港人を受け入れることを積極的に喧伝しているスタンスであり、香港人が台湾での新しい生活に移行することに対して支援を行う覚悟を持っていると伝えられています。
また、同じ中国語圏であることもあり、香港人にとっては移住後、余り違和感なく生活を再構築出来ると言う見方が多くを占めます。しかしながら、香港人の視点はやや異なっており、台湾を"明日の香港"と見る向きが強い為、終の住処として"一抹の不安が残る"と言及する層も存在します。
では英国やオーストラリア、カナダはどうでしょうか?特に英国は英国海外市民旅券を有する香港人を対象に受け入れるスタンスをいち早く表明し、一定の条件をクリアした暁には晴れて「英国人」となるルートも示されていますが、こちらの場合は、文化圏が全く異なることと、欧米諸国に横たわるアジア人蔑視(人種差別)が根強く存在する等の理由の為、これまた香港人にとっては97年返還時のトラウマが存在している先とも言われています。
以上、中国の国家安全維持法の余波は企業にも多くの損失を齎し、また個人では"留まるも地獄、離れるも地獄"と言う様相を呈して来ました。果たしてどの道を選ぶことになるのかは当事者達の選択次第となる訳ですが、簡単ではないことは明らかです。

















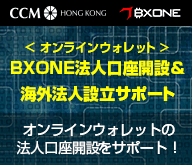

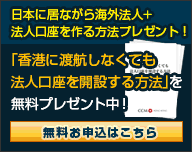





 香港
香港