- TOP »
- 法人設立お役立ち情報 »
- その他 »
- その他税務
「源泉徴収」の要否の判断を行う必要があるケースとは?
「源泉徴収」と言うのは、海外企業に対する支払いにあたって、その一部を日本国内の企業側が留保し、それを税務署に納付することをいいます。
つまり、仮に源泉税率が20%だとすると、海外企業から100の請求書が来た際、日本国内の企業側がその全額を支払うのではなく、20を源泉徴収して、80だけ支払うことになると言うことです。
この20は後日に税務署に納付する必要がある訳ですが、ここで重要なのは20の源泉所得税は(日本国内の企業側なのではなく)海外企業が負担していると言うことです。日本国内の企業側から見れば、20を税務署に納付するので、なんとなく自社に負担があるように思えますが、実際には(100の請求書に対して)合計で100しか支払っていません。
つまり、その内の20の支払い先が海外企業ではなく、単に税務署だった、と言うだけの話です。一方、海外企業から見れば、100の請求書に対して、80の入金しかないと言うことになりますが、差額の20は(日本国内の企業側を経由して、日本にある)税務署に納付されていることから考えても、この20は海外企業にとっての税負担であることが分かります。
つまり、この「源泉徴収」は、海外企業が負担すべき税金を、日本国内の企業側が"代理納付"していることに過ぎないと言うことになります。
「日本国内の企業側が源泉徴収をせずに100の支払いを海外企業に行い、その後、海外企業が自ら20の納税を行った場合」と「日本国内の企業側が20の源泉徴収を行った場合」と言うのは、(結果的に)"資金の流れが同じことになる"、と言うことです。
勿論、税務署にとっては、日本国内の企業側に源泉徴収させた方が徴税の観点からシンプルかつ容易であると言う側面があり、故にこれが「源泉徴収」と言う制度の存在意義の1つと言っても良いでしょう。では海外企業の支払いについて、「源泉徴収が必要かどうか?」はどのように判断すれば良いのでしょうか?
具体的には、以下の手順で判断します。
(1)支払いの内容
↓
(2)日本の税法を基準に判断し、「源泉徴収」が必要かどうかを判断する
↓
(3)両国の間で締結されている租税条約を考慮しても、結論が変わらないかどうか?
(1)支払いの内容
まず、文字通り、これは海外企業への支払いの内容を確認する必要があります。
大きく分けて、①商品の輸入代金、②使用料(「ロイヤルティ」とも呼ばれ、例えば特許権の使用料など)、③配当、④借入金の利子などが頻繁に登場する項目と思われます。
(2)日本の税法を基準に判断し、「源泉徴収」が必要かどうかを判断する
次に、(1)の分類をもとに、日本の税法に基づいて「源泉徴収」の要否を判断します。既に見た通り、「源泉徴収」により、税金を負担するのは海外企業です。従ってこの場合、基本的に「海外企業が日本で何らかの所得を得ているか?」と言うことを考えます。
この、日本で稼得する所得、を「国内源泉所得」と呼んでいますが、仮に海外企業が(日本の国内源泉所得を得ていたとするなら、「源泉徴収」が必要と言う考え方になると言うことです。しかしながら①商品の輸入輸入代金については、基本的に「源泉徴収」は不要であるとなる反面、③配当や④借入金の利子(日本で資金が使用されている場合)については通常は「源泉徴収」が必要となって参ります。
また、「源泉徴収」が必要な場合は、一体何%の税率となるのか?も考えなければいけません。一般的には、日本では20%(復興特別所得税も含めると20.42% )となる場合が多いです。
(3)両国の間で締結されている租税条約を考慮しても、結論が変わらないかどうか?
最後に租税条約を検討することになります。この検討に当たっては注意を要する点と言うのは、
(A)所得の源泉地に係る規定
(B)限度税率(源泉税の減免)に関わる規定
の2点です。例えば香港企業に支払う使用料(ロイヤリティー)を考えた場合、①日本の税法では20%の税率で源泉徴収する必要がありますが、②香港と日本の間の租税条約上では限度税率は5%とされています。
そのため税務署には(租税条約に関する届出書)などを提示することにより、③結果として源泉税が5%となると言うことです。
このように租税条約の存在によって源泉税率が変わることがあるので、この点にも注意が必要です。

















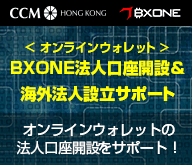

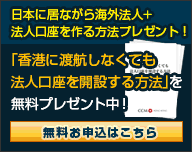





 その他
その他