- TOP »
- 法人設立お役立ち情報 »
- 香港 »
- 香港一般
英国と中国、香港を巡って発生したその思惑の裏と誤算
ここ数年に渡って香港に起こった数々の出来事と言うのは、香港のイメージの多くを毀損してしまうようなものでした。例えば2019年は「逃亡犯条例」とそれに伴う大規模かつ継続したデモ活動。2020年は「香港国家安全維持法」の制定から発生した香港民主派の徹底検挙。そして2021年は香港そのものの「選挙制度改革」と言った具合に一年毎に大きな歴史上の転換が行われたと言えます。
香港に居る民主派議員や活動家、また市民及び市民団体は諸外国、特に歴史的に大きな軌跡を残している英国や、経済的に多大な影響を与えている米国等に対して"助け"を求めるアクションを発信して来ましたが、これに対する大国達の反応はと言うと、声高に中国の行動を非難はすれど、行動としてあからさまに(中国を)刺激するような動きは"控えていた"と言えます。
こうした姿勢の奥底にある大国の真の意図と言うのは、やはり一にも二にも"ビジネスの上に成り立っている"ことに異論を唱える人は居ないでしょう。
事実、香港にとって旧宗主国であった英国については今までの過程=歴史においても幾度かこのような行動を取っています。例えばその昔、英国はアヘン戦争を仕掛けることで中国に香港を割譲させることを呑ませ、結果として当地はアヘンという"麻薬の取引"の場と転落する訳ですが、英国はこのことについて罪悪感などは一切持っていません。実際、国としても中国に公式に謝罪を行ったこともありません。
むしろ腹中では経済発展の土壌を作ることで(本国だけでなく)香港そのものを"世界に対して突出した市場を構築してやり、中国を食わせてやった"と言う自負すらあったのではないでしょうか?
また、香港の返還交渉の際も事前に自国の経済権益(HSBCやハチソン、スワイヤなどの英国系コングロマリット)をしっかりと保守することを行い、表面的な交渉経緯の中ではあくまで面子に拘る中国の顔を"立てた"形で租借延期の論議から引くと言う姿勢(敢えて"負けたように"見せる)を演出しました。
こうした英国の老獪な駆け引きは、近年の動乱のキッカケとなった"雨傘運動"の時ですら変更はせず、あの喧騒の中でも沈黙を守っていたのも今では合点が行きます。つまり、英国にとっては「権益」の確保こそが最重要課題であり、中国がその面に踏み込む姿勢を見せない限り(事実として現在でも香港の経済システムに中国はメスを入れていません)は事態静観のポジションを取ると決め込んでいたと言うことです。
しかしながら、(表面的には兎も角)こんな"緩やかな"スタンスを敷いたベースの中で向き合っていた両国の関係が本当の意味で一気に緊張を纏うことになったのはBNO(英国海外市民旅券)の一件です。
これは(英国からすると)先に制定した中国による「香港国家安全維持法」に対する西側諸国の人権擁護の一環=一種の軽いカウンター程度の意味合いであった訳ですが、これが中国習近平の逆鱗に触れることとなり、一気に対英国に対するアグレッシブな政策転換を促すこととなってしまいました。
中国はこのBNOを認めないばかりでなくBBCの国際放送の禁止、更に今では(コロナ禍を口実として)スワイヤGやジャーディンマセソンと言った英国系企業を狙い撃ちする状況にまで発展しています。
当然のことながら、英国もこれに対抗、今では(穏健派と考えられていた)バイデン政権擁する米国まで巻き込んだ形で対中強行路線へと舵を切り始めているのは周知の事実です。
まさに誤算を呼ぶ誤算、この顛末は未だ想像は出来ませんが、習近平首席が(民主主義国家でない)シンガポールを"明日の香港"のモデルと捉えていると言われていることを踏まえると民主主義なき香港の繁栄がそのゴールと言えなくもありません。そうなった際、果たしてそれを英国や世界はどう捉えるのでしょうか?
"策士策に溺れる"と言う言葉がありますが、政治力に長ける両国のせめぎ合いはより一層の深刻度を増す可能性が濃厚であり、このまま行くと、"勝者なき"政治・経済戦争の様相となるのは間違いなさそうです。

















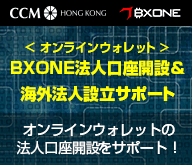

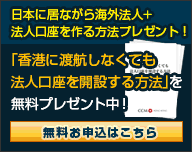





 香港
香港