- TOP »
- 法人設立お役立ち情報 »
- 香港 »
- 香港法人
租税対策がこれまで以上に加速する?「タックスヘイブン」を筆頭として存在する様々な種類とは?(2)
「タックスヘイブン」を掘り下げていくと、どこかの段階で必ず目にするのはネガティブな事件史です。印象としては一部の富裕層や企業が不当な手段を通して富を維持・享受すると言うものになりますが、実際にこうしたイメージを助長する大きな事件が今まで存在して来たのは事実です。
以下に挙げる2つの事例は、どちらも我が国における租税回避に関する事件であり、故に健全に租税効果を実現しようとする企業(及び個人)にとって、言わば"反面教師的意味合いからも知っていて損はない情報であると定義出来ます。
<事件史>
①ガーンジー島事件
日本の損害保険会社が、チャネル諸島ガーンジーに子会社を作り納税を行っていました。このガーンジー島の税制と言うのは、一定の条件を満たせば「外国資本法人の所得税(日本の法人税に相当)」の税率を選択申請できると言うものでした。具体的には(税務当局の承認を前提条件としてではありますが)0〜30%以下の比率の中から税率を選択することが可能になると言う制度です。その為、上述の損害保険会社は26%の税率を選択することで納税を行っていました。では何故"26%"の税率を選択したのかと言うと、それは当時の日本国内の税制上で"25%以下"の税率の外国・地域に関してのみ「タックスヘイブン対策税制」が適用されていると言うものだったからです。
仮にもしこの企業が25%以下の税率を選択してしまったとすると、当然のことながら上記のタックスヘイブン対策税制が適用されることになります。そうなるとこの子会社の利益すら合算課税の対象となるため国内の法人税率である30%が一律適用される羽目になってしまいます。
それを避ける意味で"26%"となる訳ですが、これを日本の税務局は不服とし、この損害保険会社の手法はガーンジー島の掲げる「外国法人税」には"該当しない"と言う判断を行います。結局この争いは裁判にまで発展することになり、最終的に裁判所は最高裁にて原告(税務局)の主張を全面的に認める判決を発表します。結果として損害保険会社は正統的な租税効果策を行ったのにも関わらず、それを根底からひっくり返されると言う顛末になってしまったケースです。
②サンリオ事件
この事件を端的に表現するとサンリオが所有する香港と台湾の子会社に於ける決算について東京国税局が噛み付いたと言うものです。国税局側の主張と言うのはサンリオ香港とサンリオ台湾の稼いだ5年分(2017年〜2021年)の所得約42億円が日本の親会社の所得として合算されるべきであると言うものでした。サンリオ側としては同社子会社自体が何れも事業実態を備えており、また適正に税務申告を行ってきたとして控訴をすることで対抗したわけですが、以下の<日本の敷いた対策>内で挙げる「経済活動基準」の達成が不十分と判断され、結果的に敗訴の憂き目を味わう形になってしまいました。
<日本の敷いた対策>
ひと言で言うと、日本のタックスヘイブンに対する対策と言うのは「タックスヘイブン対策税制」と言うガイドラインに集約されています。この税制は他の税制同様、一定の期間を経て都度見直しが施され、強化されると言う経緯を辿って来ています。その内容は非常に厳格であり、「経済活動基準」を満たす為の4つの基準(1.事業基準2.実体基準3.管理支配基準4.非関連者基準&所在地国基準)を全て充足することが必須となります。この部分に対する締め付けは改訂の度に強化される傾向が顕著であり、故に企業としては常にマイナーチェンジを念頭として備えておく必要があるでしょう。
<各国が行っている租税回避策や対タックスヘイブン規制>
最近のグローバルビジネスの流れは、以前のものと違い、オンライン化を筆頭に変化・発展してきた背景があり、従来のビジネス枠の解釈では線引きが困難になってきました。そこでOECD(経済協力開発機構)では、これらの状況に適切に対応するための税制を作る動きが最近顕著になっています。
その代表的なものが「デジタル課税」であり、インターネット全盛の現在では企業側として対策を真剣に行う必要がある可能性を含んでいます。デジタル課税の対象となるのは、例えば国内に支店・工場などの物理的な拠点がない外国籍企業などであり、さらに具体的にはGAFAのような超大手のデジタル系企業たちを標的とした税制です。
以上、今回は具体的な事件の事例紹介と日本、各国が行う対策について触れました。次回は、今回と前回の内容をまとめた総括的な論点をご紹介したいと思います。

















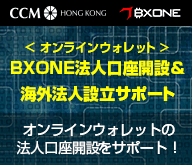

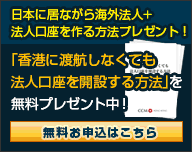





 香港
香港